筋トレを続けていると「ベンチプレスとデッドリフトは反比例する」と耳にすることがあります。
ベンチが伸びるとデッドが落ちる、デッドを頑張るとベンチが停滞する――。本当にそうなのでしょうか?
この記事では、その理由と両立のための実践的な工夫を解説します。
よくある疑問「なぜベンチとデッドは反比例するのか?」
両者は一見まったく別の種目に見えますが、実際には使う筋群や関節の安定性に共通点があります。
- 胸郭・肩まわり:ベンチでは胸郭を開き肩甲骨を下制・内転しますが、デッドでは肩甲骨を安定させつつ僧帽筋や広背筋を強く使います。
- 腰背部の疲労:ベンチの強いアーチは腰に負担をかけます。デッドでも脊柱起立筋を酷使するため、疲労が重なるとフォームに影響が出ます。
種目間で干渉が起きやすいポイント
- 握力・前腕 デッドで高重量を握った翌日にベンチをすると、バーの安定性が悪くなることがあります。
- 肩甲骨まわりの使い分け ベンチは「寄せる」、デッドは「安定させる」が基本ですが、どちらも僧帽筋・広背筋を強く使います。
肩甲骨の安定やフォームの基本はこちらの記事にまとめています → 重量を伸ばすためのベンチプレスフォーム:僕が大事にしている3つのポイント - 下背部の負担 ベンチアーチとデッドのスタート姿勢はいずれも腰椎の安定性が重要。腰の疲労が抜けないまま両方を追い込むと怪我リスクも上がります。
両方を伸ばすための実践的アプローチ
プログラム内での配置
- 同日実施する場合:ベンチ → 補助種目 → 軽めのデッド(RPE6〜7程度)
- 別日実施する場合:ベンチを週前半、デッドを週後半に分け、疲労を分散させる
頻度をずらす
ベンチ:週2〜3回
デッド:週1回(必要なら補助でヒップヒンジ系を追加)
実際の週3・1時間メニュー構成はこちら → 週3・1時間で筋トレは伸びる?実際のメニュー公開
RPEを活用する
「毎回全力でやらない」ことが両立のコツ。
RPE7〜8を基本にして、ピーキング期のみ高強度に寄せると疲労をコントロールできます。
実体験から学んだ工夫
私自身、ベンチを優先していた時期にはデッドが明らかに停滞しました。
逆に、デッドの重量更新を狙った時期はベンチの記録が落ち込みました。
その経験から学んだことは:
- 「両方を同時に最大化するのは難しい」
- 「その時期の優先順位を明確にする」
です。
例えば、ベンチを伸ばしたい3か月はデッドを維持程度に留める。逆にデッド強化期はベンチを軽めに回す。
このサイクルを意識してからは、両方とも長期的には着実に伸びています。
まとめ|両立のカギは疲労管理とフォームの精度
- ベンチとデッドは筋肉や関節の使い方が重なる部分が多く、疲労が干渉しやすい
- 握力・肩甲骨・下背部の疲労に注意
- 頻度をずらし、RPEを調整し、優先順位をつけてトレーニングすることが両立のコツ
実際に私が停滞期をどう乗り越えたかはこちらで詳しく書いています → 停滞期をどう乗り越えたか?ベンチプレス100kgまでの実録
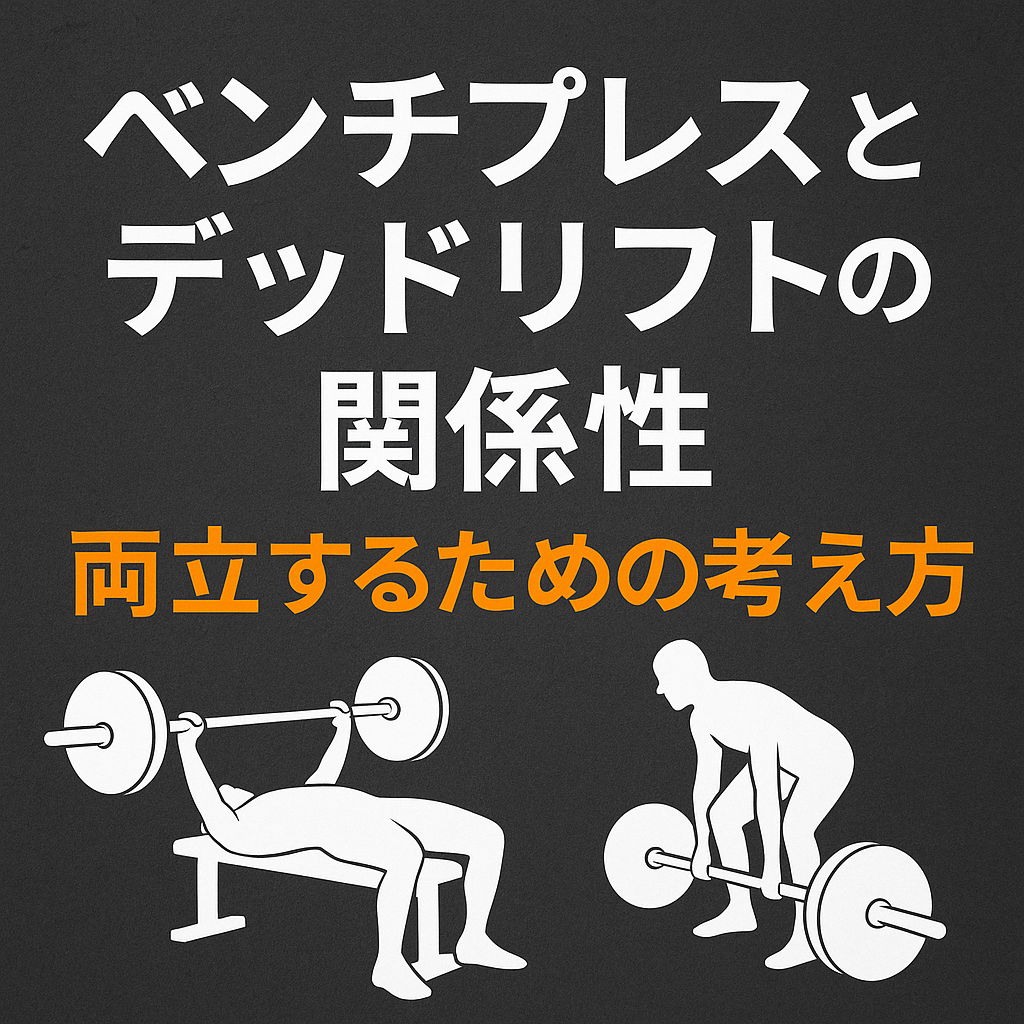
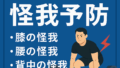
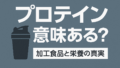

コメント